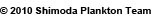1, 2. Dinophysis acuminata. 生細胞. 下田沖 (2010.5.17). Scale bar = 20 µm (1, 2 共通).
渦鞭毛植物門 渦鞭毛藻綱 ディノフィシス目 ディノフィシス科
Dinophysis acuminata
Claparéde & Lachmann 1859
Synonym:
Dinophysis borealis Paulsen 1949;
Dinophysis lachmanii Paulsen 1949;
Dinophysis boehmi Paulsen 1949;
Dinophysis skagii Paulsen 1949;
Dinophysis lachmanii Solum 1962
単細胞遊泳性。細胞は卵形〜楕円形で左右に扁平、大きさ 40-60 X 30-40 µm。細胞前端に前後を翼片で囲まれた横溝がある。前方翼片は前後長が長く、盃状、底部の幅は細胞幅の1/2-1/3程度。後方翼片は前後長が短く、縦溝に沿って後方へ伸び、縦溝左縁翼片と縦溝右縁翼片になる。縦溝左縁翼片は縦溝右縁翼片より長く、ほぼ一定の幅で後方へ伸び、長さは体長の1/2-2/3程度。縦溝左縁翼片には3本の肋がある。縦溝右縁翼片は短く長三角形。本邦産の個体では細胞後端は丸みを帯び滑らかだが、まれに1〜数個のいぼ状突起がある。鎧板表面には小さな窪みが密生する。
赤褐色の葉緑体をもつ。この葉緑体様構造はクリプト藻起源であることが知られており(Takishita et al. 2002, Hackett et al. 2003)、おそらく盗葉緑体。おそらく混合栄養性。
本種は下痢性貝中毒 (Diarrhetic Shellfish Poisoning; DSP) の原因であるオカダ酸(okadaic acid)を生成することで知られている。非常に低密度(200 cells/L)でも毒性を示すことがあるが、毒性を示さない地域もある。
世界中に広く分布し、特に温帯域に多い。本邦沿岸域ではふつうに見られる。
参考文献 References
- Faust, M. A. & Gulledge, R. A. (2002) Identifying Harmful Marine Dinoflagellates. Smithsonian Institution Contributions from the United States National Herbarium. Volume 42: 1-144. (http://www.nmnh.si.edu/botany/projects/dinoflag/index.htm)
- 福代康夫 (1990) Dinophysis acuminata. In 日本の赤潮生物(福代康夫・高野秀昭・千原光雄・松岡數充 編). 内田鶴閣圃, 東京. pp. 34-35.
- 福代康夫・井上博明・高山晴義 (1997) 渦鞭毛植物門. In 日本産海洋プランクトン検索図鑑(千原光雄・村野正昭 編). 東海大学出版会. pp. 31-112.
- Hackett, J.D., Maranda, L., Yoon, H.S. & Bhattacharya, D. (2003) Phylogenetic evidence for the cryptophyte origin of the plastid of Dinophysis (Dinophysiales, Dinophyceae). J. Phycol. 39: 440-448.
- Steidinger, K.A. & Tangen, K. (1996) Dinoflagellates. In: Identifying Marine Phytoplankton. (Tomas, C.R. Eds), pp. 387-584. San Diego: Academic Press.
- Takishita, K., Koike, K., Maruyama, T. & Ogata, T. (2002) Molecular evidence for plastid robbery (kleptoplastidy) in Dinophysis, a dinoflagellate causing diarrhetic shellfish poisoning. Protist 153: 293-302.