霞ヶ浦における有機物のサイズ組成およびその化学的酸素要求量との関係
金子 卓生 指導教官:濱 健夫
◆目的
近年、霞ヶ浦や琵琶湖といった閉鎖性湖沼における水質汚濁は、窒素・リンの排出規制といった流域発生源対策が行われているにも関わらず、悪化の傾向が見られることが報告されている。しかし水質汚濁に関わる主要な因子の1つである有機炭素、特に溶存態有機炭素(DOC)の化学的特性および生態学的・地球化学的役割は、生物活動だけでなく人間活動の影響もあって未だに十分には解明されていない。そこで本研究では、地球化学的手法として有機炭素のサイズ別分画、環境化学的手法として化学的酸素要求量(COD)を測定し、霞ヶ浦における有機炭素の特徴や分布、由来を考察することを目的とした。
◆方法
2000年7月から12月までの半年間、国土交通省霞ヶ浦工事事務所と共に、霞ヶ浦において水質基準点を含む6ヶ所(釜谷沖・高浜沖・湖心・掛馬沖・土浦港内外)から表層水のサンプリングを月に1回行った。試水は孔径0.7μmのガラス繊維濾紙(WhatmanGF/F)を用いて懸濁態有機炭素(POC)とDOCに分別し,元素分析計およびShimazu-TOC5000により炭素量を測定した。全有機炭素(TOC)はPOCとDOCの和で求めた。濾液はさらにホローファイバーカートリッジ(H1P190-20:分画分子量10kDa)を用いて、低分子量画分(LMW)と高分子量画分(HMW)に分画した。次に日本工業規格に定められた過マンガン酸カリウム法を用いて、各成分(TOC・POC・DOC・LMW・HMW)に対応するCODを測定した。CODPOC値は直接分析できないので、CODTOC値からCODDOC値を引いて求めた。また、chl.a値については霞ヶ浦工事事務所から参照させていただいた。
◆結果・考察
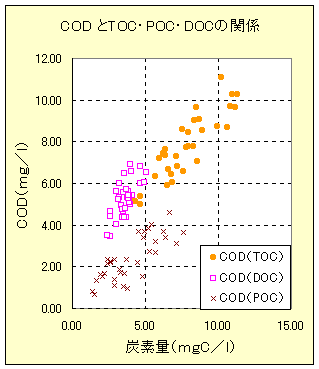
(1)炭素を酸化するために必要な酸素消費量がPOCではDOCの約50%しか必要としないことから、CODと有機炭素の関係では、酸化されやすいPOCと酸化されにくいDOCの違いが明確に見られた(下図参照)。このようなPOCの不安定さは、POCの約70%を植物プランクトンを占めることを考慮すると、生きた細胞の成分ほど酸化されやすいことが原因と考えられる。
(2)さらにDOCに注目すると、LMWとHMWが約5:4の割合で存在していた。ここで両者のCODを測定してみると、HMWは酸化されやすく、LMWは酸化されにくい傾向が認められた。この結果,DOCが酸化されにくい原因は主にLMWにあることが分かった。これはLMWは安定でHMWは不安定という最近の報告と一致する。さらにchl.a値との相関関係と酸化されやすい特性により、HMWには生物由来の有機物が多いことが示唆された。一方、LMWは酸化されにくい特性を持つことから、難溶解性物質を含んでいることが示唆された。