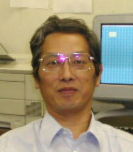
私は、今は消滅してしまった東京教育大学(筑波大学の前身)の農学部で育種学を勉
強した後、博士課程からは私の恩師である原田宏先生(筑波大学名誉教授)に師事し
、植物の組織培養の研究を行い、その後、Agrobacteriumに興味を持ち、植物におけ
る遺伝子組換えの研究もしてきました。しかし、その間ずっと興味を持っていた課題
は、植物の発生・分化、特に形態形成です。なかでも、胚発生の機構解明は農学部時
代より引き続き研究をしている課題で私自身最も興味を持っています。最近では、私
の研究室の学生達自身がいろいろな課題に興味を持ち、さまざまな研究をしています
が、いずれにしても、植物の発生・分化という大変難しい課題に取り組んでおり、そ
う簡単に明確な解答がでるものではありませんが、地道に研究を続けて行きたいと思
っています。私が学生達に望むことは、興味を持てる課題を探して自分でとにかく一
生懸命・気長に研究を続ける気持ちを持って欲しいことです。先生からあてがわれて
おもしろいと思っていない研究は長続きしませんし、研究のドライビングフォースに
なりません。自分でおもしろいと思うことが何よりも大切です。
ところで、私自身は雑用で忙しくしており、自分自身で研究をする時間がないのが残
念でなりません。そんな状況なので、生命科学研究の技術は日進月歩なので、技術的
には学生達、特に大学院生にかなわないと思っていますが、研究の進め方、理論的な
概念作り等では絶対に学生達に負けないつもりで努力しています。
私の雑用の中身についても少し触れておく必要があると思います。私が現在所属して
いる筑波大学生物科学系は通常の大学の理学部生物学科で、基礎研究に主眼をおいて
います。しかし、私自身は農学部の出身でいつも頭のどこかに応用研究に対する思考
があります。このため、Agrobacteirumの研究を始めたときも単に形態形成(クラウ
ンゴールや毛状根)の機構解明にとどまらず、その応用にも目が向き、その結果、高
等植物への遺伝子導入技術の開発、毛状根を用いた有用2次代謝物質の生産等の研究
も外部の人達との共同研究の形で実施してきました。そのような経緯の中で、日本国
内では早くから高等植物の遺伝子組換えを実行してきた関係で、遺伝子組換え植物の
育成・管理・利用に必要不可欠なさまざまな規則(組換えDNA実験指針、植物防疫法
、遺伝子組換え植物の環境への影響評価、遺伝子組換え食品の食品としての安全性等
)を制定する作業に従事することとなり、文部省ばかりでなく、厚生省や農林水産省
の研究者達とも相互交流を深めつつ、日本全体の関連分野の研究基盤を構築したり、
遺伝子組換え植物(技術も含め)の社会的受容に向けた活動をせざるをえなくなりま
した。その結果、私の研究室では基礎研究を中心に進めていますが、対外活動として
は、応用的な側面が強くなっており、外部の人からはよくバイテクを研究課題として
いると思われがちですが、実際の研究自身はすごく基礎的なものです。
いずれにしても、私の研究室のモットーは、”植物形態形成の重要な制御機構を明ら
かにし、世界のメジャーになること”です。意欲のある方の参加をお待ちしています
。