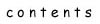|
つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2002) 1: 10-11.
創刊号に寄せて ―人類進化の未来は学生諸君の頭脳に在り―
關 文威
(元 筑波大学 生物科学系)
2002年7月上旬、科学雑誌Natureに掲載された論文[1]の紹介報道が一般社会にも駆け巡った。それは、700万 年前の猿人(学名Sahelanthropus tchadensis)の頭骨化石がアフリカ中部のチャドで発掘され、類人猿と人類と の進化の分岐点付近における詳細な研究が将来可能になるとして、「生命の希望」を意味するトゥ−マイ猿人と名付 けられたという論文の紹介である。この進化の分岐点は、DNA解析に基づく分子進化学的な研究に拠れば、500万年 から700万年前にあったと推定されていた。しかし、この時期の人類化石がまったく発見されていなかったために、 霊長類の系統樹における空白「ミッシング リンク」と呼ばれ、その時期の人類は水辺環境に適応している現存種テングザルの様な水棲であったとする学説さえも流布されていたのである[2]。 一般に、生物種の出現と絶滅は100万年の時間単位サイクルで起っていることが、化石の研究によって示されて いる。このサイクルを人類に限定してみれば、猿人類から原人類、そして旧人類から新人類へと進化するほど加速 されている[3]。すなわち、種として存在する期間は、人類が進化した種になればなるほど短縮されて、更に進化し た新種の人類が出現し易くなっている。人類が出現してから700万年が確かに経過しているならば、現在こそ現生 人類が進化して新種を形成している時期に相当する。 ここに、生物が進化に用いる生命エネルギーは、生物細胞の発生可能な全生化学エネルギーから基礎代謝エネル ギーを差し引いた余剰のエネルギー部分から賄われる。したがって、原始生物から人類までの進化過程すべてにお いて、生物種とエネルギー発生機能との進化には密接な関係が認められているのである[4][5]。従来の科学では、エネルギー発生機能の進化は、発酵代謝から嫌気的呼吸に進化してから、微好気呼吸を経て好気的呼吸へと進化する 遷移現象として捉えられてきた。しかし近年、ノーベル賞受賞者Mitchell[4]の化学浸透圧理論が生物進化との関係 でも追求されるようになってから、エネルギー代謝機能の進化を電子伝達系の進化として解析することにより、よ り詳細な進化現象の研究が可能になってきている。 生物が余剰の生化学エネルギーを進化に充てた結果として生ずる顕著な現象は、生命の起源を担った単細胞の原 核生物が真核生物となり、さらに真核生物が単細胞生物から多細胞生物となる形態的な進化である。そして約13億 年以前に、完成度が極めて高い電子伝達系機構を獲得した生物細胞は、生命維持に必要な基礎代謝エネルギーを遥 かに超える生化学エネルギーを発生させ得るようになった。この余剰の生化学エネルギーが生物種の進化に充てら れる機構の数理解析として、近年急速に一般社会にさえ関心を持たれるようになったKauffmanの研究論文がある[6]。 この研究の魅力は、遺伝子の振る舞いが簡単な数理統計モデルとしてシミュレーションできることを示すばかりか、 系統分類と細胞型数の関係をもって進化の予測をもなされ得ることを示しているところにある。 この数理モデルを論議の対象にしている霊長類のみに限って応用してみれば、種進化は系統樹の頂点にある小枝 の先端に向かう方向にしか進行することができないことが判る。例えば、霊長類(サル目:Primates)とともに哺 乳類(哺乳綱:Mammalia)に属するウマ亜目(Equus)内の種間交配の代表例であるラバは雄ロバと雌ウマとの種間 雑種であるが、雑種不稔性であり、新種にはなり得ない。この現象は、Kauffmanの数理モデルに拠れば、哺乳類の 近縁種間における種保存の辺縁で生じた状態サイクルの最小摂動として論理的に説明できる。ところが、ギリシャ 神話に語られているミノタウロス(頭が牛で身体が人間の怪物:Minotaur)は、系統分類上「目」間の雑種、すな わち哺乳類(哺乳綱:Mammalia)に属するウシ目(Artiodactyla)の雄ウシとサル目(霊長類)(Primates)の雌ヒ トの交配であり、Kauffmanの数理モデルに拠れば雑種の出現は不可能である。もっとも、この雄ウシはゼウス神の 化身であるから、雑種の形成が可能なのであろう。神話時代以降の人類の種間雑種としては、ポルトガルで発掘さ れた少女の化石(Lagar Velho)が現生人類(Homo sapiens)とネアンデルタール人(Homo neanderthalensis)の雑種であるとDNA鑑定に拠っても確認されている[7]。この人類における種間交配も、Kauffmanの数理モデルに拠って、哺乳類の近縁種間における種保存の辺縁で生じた状態サイクルの最小摂動として説明可能であろうが、この雑種が特定人類として定着しているか否かは、現在のところ確定的ではない。 以上の科学的根拠に基づいて、人類進化の方向性を概観することは容易であろう。卓越した科学者Teilhard de Chardinは、20世紀前半に、自らも従事した北京原人発掘調査などの古生物研究を基に、現代の先端科学によって 導かれている研究結果と同様な「生物圏における生物進化の推移」に係わる見解を提示している[8]。すなわち、細 胞型の少ない生物ほど遠心的な分化をもたらす多様な生物種群へと進化してきたが、10万個の遺伝子と370個の細 胞型を有する人類のレベルに達すると、進化は求心的な方向へ求めざるを得なくなる。この人類の進化過程は根本 的に頭脳の発達(cephalisation)へと収斂して、現生人類から新種の形成過程として超人化現象(ultra- hominisation)が進行すれば、単一の精神機構へと導かれるのである。ここに、形態的な超人化現象としては、単 に頭脳が増大すれば良いのではない。何故なら、旧人の一種ネアンデルタール人は、現生人類よりも長身であった ばかりか、脳容積が大きかったからである。超人化現象には、視覚や知的思考など司る頭頂葉などの質的な頭脳の 発達が重要なのである。因みに、二十世紀最高の科学者Albert Einsteinは頭頂葉が異常に発達していたことでも遍く知られている。そして、超人は余剰の生化学エネルギーを現生人類より多く発生し、多様に分化した多数の精 神社会を形成する方向に用いられることが期待される。ここに、現生人類のみが、特に宗教家(例えば禅の呼吸法) や武道家(武息法)の努力によって、呼吸機構の係わる通常細胞と酸素要求型細胞とを意識的に切り替える術を既 に開発して、実践していることに注目したい。これら一部の現生人類が生命エネルギーを精神と肉体との生理活性 化を必要とする時機を認識した時には、酸素要求型細胞は随意的に通常細胞の機能を遥かに超える生化学エネルギー を発生できるのである。 論語に「學而不思則罔、思而不學則殆」の教えがある。筑波大学生物学類の学生諸君は知性的に優れた現生人類 として選ばれた集団であるから、頭頂葉などを極度に発達させるために「博く学び、その道理を深く思索研究する」 努力の限界にまで挑戦して、超人への進化を加速されるように念願している。 参考文献
Contributed by Humitake Seki, Received August 7, 2002.
©2002 筑波大学生物学類
|