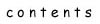|
つくば生物ジャーナル Tsukuba Journal of Biology (2003) 2: TJB200312HK.
特集:下田臨海実験センター設立70周年記念
加藤 秀生 東北大学大学院理学研究科教授
(浅虫臨海実験所長、下田同窓生、動物発生学)
私は現在青森県の浅虫というところにある東北大学の臨海実験所で仕事をやっているのですが、教育大学時代に私がいた下田の研究室の、渡邊先生の物の考え方は、やはり自由な発想をさせるということでした。かなり学生の自主性というのを重んじていました。学生にとって、できるだけ仕事がしやすいような雰囲気というものをつくることが大切である、ということを下田で教わったように思います。
東北大学大学院理学研究科付属浅虫臨海実験所
近年は、医学を中心にした生物医学的なものの発想が、随分出てきましたね。それはある意味では正しいのでしょうけれども、そうではなくて、やはり生き物の多様性を生かした、もっと幅広い進化というものを視野に入れた理学的生物学の研究をやっていくというのは、臨海実験所の使命だと思います。また、それができる特権を持っている。なぜかというと、やはり海岸に皆さん出てみられると分かるように、いろいろな生き物がたくさんいます。下田は特に、まだ海岸がきれいですから、そのようなところで、いろいろな発想法を持ちながら、研究材料としてはどの生き物がいいか、幅広い生物群から選ぶことができます。つまり、海岸は生物の多様性の宝庫であり、臨海実験所はそれを扱える高度な研究技術を持った場所なのです。 そのような意味において、日本が基礎生物学研究に力を入れるとするのであれば、海洋生物の研究の場である臨海実験所に力を入れなければなりません。これは基礎生物学の面から日本が国際的に貢献できるための、一つの活路ではないかと思うのです。この意味からも下田は、非常に重要な位置を占めていたということは間違いないです。
Contributed by Taketeru Kuramoto, Received October 21, 2003, Revised version received October 28, 2003.
©2003 筑波大学生物学類
|
 私は5年間、大学院の博士課程修了まで下田でお世話になりました。
その当時は、教育大学の大塚キャンパスが、ちょうど大学紛争が終わっ
た後の余波が残っていたことから、キャンパスの中に入ることのできる
時間というのがかなり厳しく決められていました。夕方の早いうちから
正門が閉じられてしまって出入りができないという状態だったのです。
我々は下田の臨海実験所にいたものですから、そのような制限というのは一切なくて、ある意味では、古き良き自由な大学という雰囲気がずっと保たれていました。そのような意味で、臨海実験所にいた我々は、大塚にいた同僚と比べると、随分恵まれていたというような記憶があります。
私は5年間、大学院の博士課程修了まで下田でお世話になりました。
その当時は、教育大学の大塚キャンパスが、ちょうど大学紛争が終わっ
た後の余波が残っていたことから、キャンパスの中に入ることのできる
時間というのがかなり厳しく決められていました。夕方の早いうちから
正門が閉じられてしまって出入りができないという状態だったのです。
我々は下田の臨海実験所にいたものですから、そのような制限というのは一切なくて、ある意味では、古き良き自由な大学という雰囲気がずっと保たれていました。そのような意味で、臨海実験所にいた我々は、大塚にいた同僚と比べると、随分恵まれていたというような記憶があります。